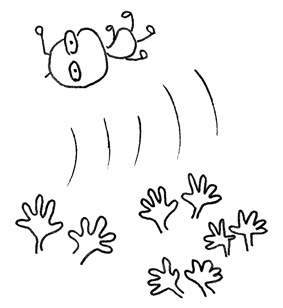|
2月5日(火)
「例の件、気になったんでメールしました。何がどうなったかわからないですね。コセムラクンに対してちょっと失礼な話に聞こえるんですが......いきさつを教えてください。大切な友人をいじめたようなら、ぼくは許しませんから」
デザイナーS氏からそんなメールが入ったのは、一月の銀座会合以来P社から再び連絡が途絶えて一ヶ月になろうかという頃のことだった。
S氏というのは、僕がこの世界で最も尊敬しているデザイナーの方で、そもそも最初にP社の件を僕に紹介してくれた人物である。僕にとっては雲の上の憧れみたいな存在であり、そんな方から「大切な友人」などと言われた日には、面映ゆくて恐れ多くてどうしてよいかわからないところだが、それはそれとして、僕はプロダクションP社、代理店D社、そしてクライアントC社に関する昨年末からのドタバタの顛末を、メールで伝えた。すぐに返信が来る。
「(A氏は)コマーシャルの人なので、ちょっと気になりました。もちろん良いヤツだけど、ひょっとして悪気なく失礼なことをしているんじゃないかなと思い、だったらお説教してやろうと思って」
コマーシャル。それが一体全体いかなる業界で、どんな人種が棲息しているのか、僕はよく知らない。僕の周りには、かつてCMをバリバリしていたけれどにすっかり嫌気が差して、雑誌やドキュメンタリーの世界に来た、という人が結構多い。P社の話を紹介してもらったばかりの昨年一一月頃、S氏からこんなメールが届いたことを、僕は思い出した。
「今日届いたテルマを読んでいて、『余計な事をしてしまったんじゃないか』と不安を覚えました。農業の世界でこんなにも優秀な編集者を、コマーシャルの世界に紹介してしまったことが。自分自身は(コマーシャルを)さんざん嫌っているのにね。Aは正しい事をちゃんと知っているので、安心はしているけど、そうはいってもクライアント様々の世界だからね......。良い経験にはなると思うけど、志をもって、コマーシャル以外の書き物をそれ以上に情熱を持って続けてください。テルマから得た日本の風景は自分の隅っこにちゃんと残り続けて、豊かになりたい自分のために、時々風を運んでくれますから」
この時、僕はD社との面接だC社とのプレだと、例のジェットコースターに巻き込まれていた時期だったので、正直、S氏からのこの助言の真の意味を掴み切れていなかった。だけど今、改めてこの文面を読んでみると、その真意が身にしみてわかる。
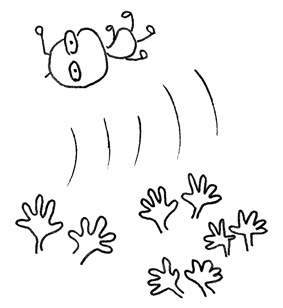
2月21日(木)
取材で山口県下関市に滞在。夜、関門海峡に面したホテルのバーでカメラマンK氏と飲んでいると、彼が言った。
「ことによるとP、D社は、C社のPR誌の仕事が先延ばしになるかもしれないことを、知っていたんじゃないでしょうか」
この転職話、僕は本当に信頼できる相手以外ほとんど内密にしていたが、K氏はその中でもとりわけ深く介入し、様々な情報を集めたり助言をしてくれた人物である。工学系出身の彼の思考は常に情緒的な要素を省いた論理的なもので、僕はそれにをかれることがしばしばある。K氏の一言に、僕はそういわれてみれば??と首肯した。
思い起こせばC社へのプレゼンテーション。あれが分かれ目だったわけだが、当初P社側は僕にもその場に同席してほしい旨を依頼してきた。が、ある段階から「やっぱりいいです」的なニュアンスに変わった。P、D社だけでやるのでとりあえず大丈夫です、みたいな。忙しいこちらの身をってくれたものと、当時の僕は思っていたけれど、そういえばあの時、何となく裏にD社の意向が見え隠れしていた。
「そうかもしれな......」
僕はそれを思い出しながら呟いた。P社が最初から僕をかつごうとした、とは考えにくいし僕もそうは考えたくない。が、D社は別だ。クライアントに近いポジションにいる代理店としては、この話が延期になるかもしれないことは、ある段階からある程度把握できたのではないか。織り込み済みだったのではないか----。
「代理店というのはどちらに対してもいい顔をしますからねー」と、これは別の人が別の時にふとこぼした言葉。

3月5日(水)
P社A氏からメールが入る。ほぼ2ヶ月ぶりのこと。
「例の件ですが、相変わらず止まったままで、この先いつ進展するか、わかりません。こちらとしても憮然とした気持ちなのですが、相手先の社内事情もあるようで......」
憮然とするのはこっちの役回りだっ、と怒鳴り返したい思いをぐっとこらえ、ここへきてようやく僕は、この「転轍機を探す旅の記録」の第一部を終わらせる踏ん切りがついた。
思い起こせば一〇月中旬から四ヶ月近くにわたって巻き起こったこのドタバタは、いま現在、何一つ形にもなっていなければ結果的に何も残しちゃいないけれど、僕の中には様々な思いをもたらした。この場をお借りして、少しばかりそれを整理してみたい。
これまで僕は「新雑誌を創刊するのでスタッフとして参加してほしい」という旨の誘いを、都合三度ほど受けたことがある。一つは知人のデザイナーとコピーライターが立ち上げた企画で、編集の責任者をしてほしいということで、非常にユニークな媒体で興味深かったのだけれど、いかんせん制作重視で営業的にとても「売れる」見込みのあるメディアではなく、しかも肝心のお金集めや営業をする人間(つまりプロデューサー)が不在だったため、結局実現しなかった。
二つ目はある健康食品の企業がスポンサーになり、「食と健康」をテーマにした雑誌媒体を出すということで、僕は外部スタッフとして参加した。企画立案や取材、撮影などに協力し、四号までは出たものの部数が伸びず、一年で休刊となった。
そして三つ目はわりと最近のことだが、心理学をテーマにした女性誌があり、部数低迷によるスタッフ全取っ替えの一大リニューアルをする、ということで声がかかった。けれども編集長候補になっていた人物が、そもそも僕の苦手な人間だったし(その人から声がかかったのは驚きだったが)、話を聞いた限りでは「どうも実現しそうにないな」という感じがしたので、お断りした。結局その話も、最終的に版元が「編集スタッフ総入れ替え」という大なたを振るいきれずに頓挫した。
つまり何が言いたいかというと、この手の話はまあそれほど多くあることでもないけれど、まるっきりないという話でもなく、さらに言えばその八〜九割が頓挫する、というのは、一つのセオリーだ。
今回のP社、D社、C社三つ巴のこの一件がどうだったかというと、当初は僕も過去の経験上かなり懐疑的だったし、それなりに警戒もしていた。が、事態が思いのほか急展開したことと、この手の話が霧消するケースにありがちな「中間業者」の存在、つまりうさんくさいプロデューサーだの後ろ暗いプロダクションだのといった存在がこの件に関してはほとんど介入しておらず、D社、C社という大手の代理店とクライアントが直接出張ってきていたため、かなり精度の高い話だと判断し、本腰を入れた。
馴れない街で触覚の折れた虫さながらにさんざん迷いながら、打ち合わせでP社へ日参し、アイデアをひねり出してプランを提出し、企画書を書いて、ダミー版まで制作した。それは僕にとってまさに目の回るような忙しさではあったけれど、今にして思えば全くのボランティアで、いいように利用されただけのようにも思えるけれど、それでも久しぶりに自分の知らない世界を垣間見るワクワク感に満ちた時間ではあった。

しかし結果的には実現しなかった。クライアントのエゴなのか代理店の狡猾なのかプロダクションの怠慢なのか、その辺のことは僕にはわからない。
最初は「一月末からぜひ!」と頭を下げられ、次には「四月から----」ともみ手をされ、そして最後は「恐らく八月くらいから......」と、うつむき加減で言われ、今に至る。
次に動きがあるとすれば、今年の七、八月頃ということになるが、その時果たして僕がどんなポジションで何の仕事をしているか、それは全くわからない。「こせさーん、お座敷の準備が整いましたのでお願いします」と声がかかっても、こちらは別の座敷で「魚鳥木」の真っ最中かもしれず、そうなれば今度はこちらから断らざるを得ない。
何より僕はこの数ヶ月というもの、全国の農村や地方都市を歩くいつもの旅が、非常に新鮮でことのほか貴重なものであることを、改めて自覚した。愛媛の段畑、福江島の離島医師、青森の津軽鉄道、そして山口のハナセイバー......どれもこれも素晴らしい出会いで、他誌では絶対に巡り会えない物語ばかりだった。改めてこの仕事の面白さ、欠けがえのなさを強く再確認した。
折しも先日、情報誌編集者のS氏と会った時、この転職話が事実上ストップした状態にあること、動きがあるとすれば半年後になるであろうことを僕が伝えると、彼女は「良かったですね」と言った。その真意が掴みきれずに訊き返そうとしたら、さらにこう付け加えた。「冷静に判断できるじゃないですか」
その通りだ、と思う。
こういう話の決め手は、何よりも「タイミング」だ。どれだけ水が合おうと、条件が良かろうと、タイミングを逸すれば水泡に帰すし、逆もまた然り。この件が次にどういう展開を見せるのか(もしあれば、の話だが)それはわからないけれど、その時どうなるか、全てはタイミング次第である。
何か動きがあれば、すぐにテルマでオンタイムに報告します。それまではとりあえず、全五回にわたりみなさんの耳目を集めたこの短期集中連載、ひとまず第一部終了といたします。
(2008年3月14日発行『TALEMARKETvol.56』より)
|