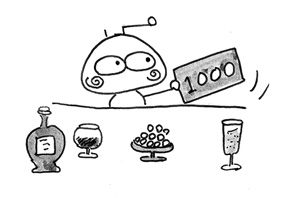|
12月21日(金)
街にはジングルベルが流れ、師走の慌ただしさと相まって、この時期は毎年恒例の躁状態。年末進行と来年分の仕込みで忙しいことこの上なく、プロダクションP社・A氏と約束した会合は、延び延びになっていた。
「飯田橋まで報告に行きます」とA氏は言うものの、互いに超多忙の身、なかなか時間を合わせられない。業を煮やしたのか焦ったのか、この日の夜、A氏から電話が入った。
「直接顔を見て話さなくちゃ、と思っていたんだけど、どんどん時間が過ぎてしまうので、とりあえず電話で大変申し訳ないんですが、この間のプレの報告をさせていただきます」
「流れたんですね」
いい加減この件にうんざりし始めていた僕は、つい皮肉っぽい口調でそう言った。が、A氏は、
「イヤイヤ! 全然逆! プレそのものは大成功だったんだよ」
慌ててそう言うのだった。
「D(代理店)から四名、うちから三名、C(クライアント)は局長以下五名が出席して、C社本社でプレをしたんだけど、コセムラクンの作ってくれた企画書やこちらが用意したデザイン案はすごく感触が良くて、向こうも『こういう雑誌にしたいねー』って、すごく乗り気でね」
「じゃあ企画OK、人選NGってことですか」
「え? というと?」
「つまり僕では役者不足だと」
「ええ!? とんでもない! 実は企画内容の話は二〇分くらいで済んじゃって、その後はずっとコセムラクンの話でもちきりだったんだよ。C社の局長なんか、あの本……テルマだっけ?コセムラクンが作っているあの雑誌すごく気に入ったみたいで、『これ一冊もらっていい?』なんて言って持ち帰っちゃったくらいでさ。『センスいいし写真もすごく上手だし、この人本当に逸材だなー』って、ベタ褒めだったんだよ。代理店も自信満々で、『超一流の編集者四〇人以上を面接した中から、選びに選び抜いた人材です』なんて言っててさ、でもホントにそれくらい面接してたらしいけどね。すごい競争率だったんだよ実際」
「はぁ……」
「そんな感じですごく盛り上がって好感触だったものだから、『じゃぁいつから始めましょう?』という話になったら、C社が『うーん、来年の八月くらいかなぁ……』なんて言い出すわけ。それで『おいおいちょっと待ってよ』という感じで----」
つまり、こういうことらしい。現在C社はPR誌の制作を別のプロダクションに委託しており、すでにそこと来年度(二〇〇八年)の企画や構成を決定してしまった後なのだという。
それを反故にしてP社に切り替えるということは難しく、そうなるとP社=D社ラインによる新制作体制というのは、二〇〇九年一月号からのスタート。そこから逆算して準備期間を四ヶ月とすると、制作は八月から??これがC社から提示されたシナリオというわけだ。
「話が違うじゃないですか!」と、P・D社はいきり立ったらしい。それはそうだろう。当初は一月スタートもありという腹づもりで、P社もD社もそして僕も、ジェットコースターのような準備作業に追われまくったのだ。アクセル吹かしまくり、「いつでも来い」の臨戦状態で鼻息荒くスタンバっていたのに、いきなり手綱を引かれ足止めを食らったような具合である。
しかし、決定権はあくまでクライアント。D社とP社がいくら突き上げようと、所詮は代理店とプロダクションの空騒ぎに過ぎない。
「なるほどね……」
半ば想定していたことではあるものの、それでも僕は失望を禁じ得なかった。そんな気配を察したのかA氏が慌てて訊ねる。
「あの、コセムラクン、ウェブの方とかはどう?」
「は?」
「いや、実はね、C社が一番気にしているのは、コセムラクンのことなんだよ」
「はぁ」
「つまり、これだけの人材だからグズグズしていると他社に取られるんじゃないかって焦っているんだ。それでとりあえず当面はC社のウェブマガジンの方の編集に携わってもらって、それで雑誌の方の準備が整ったらそっちに移行してもらう、ということも……」
「つなぎですか」
「いや、うん、まあ……」
「……それって必ずしも僕じゃなきゃできない仕事だとも思えないし、気を遣ってわざわざ仕事を作っていただいている、という感じがものすごくするので、それは心苦しいから遠慮します。そもそもウェブはよくわかりませんし」
「そう……」
A氏が溜め息混じりに相槌をうつ。それでも僕は確かめておかなければならないから、
「じゃあ来年の四月からそちらへ----という話もナシですね」と、追い討ちをかけるように念押しした。
「まぁ……とりあえず四月から来てもらって、準備を進めるという手もあるんだけど……」
「でも、まだ具体的には仕事がないんでしょう」
「そうなんだよね……」
僕はちょっとばかりキレた。
「あのですね、そもそも僕は今の仕事が嫌だとか他所へ移りたいとか、そういうネガティブなモチベーションでこの話を受けたわけでは一切ないんですよ。そちらからオファーされた仕事が純粋に面白そうで、やってみたいと思ったからだけなんです。でも、肝心のそれがどうなるかわからないというなら、今の雑誌を辞める理由なんて、僕には全くありません」
「そうだよね、いや、うん……それは重々承知しています。本当に申し訳ない」
A氏はそう謝ってから、
「要するにC社もD社も、何とかしてコセムラクンのことをつなぎとめておきたいんだよ。もちろん弊社だってそうだけど、でもぼくとしては、引き抜くという以上はコセムラクンの人生に対して相応の責任を負うことだから、口先の空約束ではなく、あくまでもきちんと体制を整えた上で、安心してお迎えできる状況を作りたい、というのが本音なんです」
この時、僕はA氏の置かれている状況がよくわかった。プロジェクトの延期が最もこたえるのは、CでもDでも、ましてや僕でもない。それはP社だ。副社長であるA氏は、この案件に対して全責任を負っている。CやDは好きなことをいくらでも言えるけれど、それは所詮、外野の言いたい放題に過ぎない。無責任なその言動に、しかし振り回されて言いなりにならざるをえないのが、プロダクションの立場というものだ。
なのにA氏は、クライアントや代理店の意向よりも、僕の立場を尊重しているのである。その姿勢は、賞賛に値した。あるいはP社というプロダクションは、それだけクライアントや代理店に対して発言力を持っているということの裏返しなのかもしれない。
「----わかりました」
僕はそう答えた。それ以外に何と言えばよいのだ。
A氏自身は、まだ自分でも納得がいかないらしく、C社に対してさらに詳しい状況を調べておくので年明け早々に会いたい、という。僕達は一月初旬のスケジュールを調整して段取りを決め、電話を切った。

12月24日(月)
師走の慌しさに取り紛れつつも、なぜこの件がこんな風に後手に回ってしまったのか、僕はその理由が知りたかった。代理店やクライアントの内部事情に関わることなので、A氏はその辺を曖昧にしていたが、僕は別ルートで調べてみようと思った。まるで探偵みたいだが、この手の情報戦は得意だ。
リサーチの結果、判明したのは、そもそも最初にC社がD社に対してPR誌のリニューアル依頼を行った際、D社側はしばらくこの案件をほったらかしにしておいたらしい。それが最大要因。最初の段階で敏速に対応していれば、こんな風に後手に回らずに済んだのだろうが、D社がグズグズしている間にもC社は翌年度の企画を進めなければならないわけで、やむなく現在のプロダクションに引き続き制作依頼をした、という顛末。九月になってD社のミスターDが担当になるやすぐにこの話を聞きつけて動き始め、P社と一緒に追い上げをはかったものの、時すでに遅し。結局、最初に話を受けたD社のお偉いさんがグズグズしていたせいで、タイミングを致命的に逸した、ということである。
「これだけ人を振り回しておいて、電通は無責任だ」と、A氏はこぼしていたが、僕から見ればそんな曖昧な状況で見切り発車をしようとしていたP社、D社の仕事の仕方そのものに疑問を禁じえない。リニューアルスタートがいつになるのか、最も肝心なその部分をグレーにしたままでプロジェクトを動かすなんて、あまりにリスキーかつ常識はずれだ。
実はP社からスタッフ集めを依頼された時期あたりから、僕はその辺のキナ臭さを何となく感じ取っていた。だから最初こそ何人かライターやデザイナーに声をかけたものの、すぐに中断したのだ。集めるだけ集めておいて「やっぱり中止します」では、あまりにも格好がつかないし無責任過ぎる。ヘッドハンティングというのは、それくらい緻密な戦略をもって臨むべきことだ。そういう目で見ると、D社、P社の仕事の進め方はあまりにも杜撰にしてお粗末だったと言わざるを得ない。

12月25日(火)
「悪いことばかりイメージしていると、物事は実際にそっちに転がってしまうから、何事も良い方に考えるべきですよ」
友人U氏の言葉だ。僕の思考には一つの癖がある。それは、常に最悪のケースを想定しておく、というもの。期待して裏切られた時の衝撃を緩和すべく、長年の痛い経験から自然に培われた心のリスクヘッジ。だけどU氏の理論に従うなら、その思考自体が悪い結果を招いているということか……?
それはさておき、二ヶ月余にわたったこの騒動は、わが身からやや離して見てみると、なかなか興味深い出来事だ。職業病かもしれないが、自分に降りかかったこの二転三転・紆余曲折のドタバタ劇は、案外ネタになるんじゃないだろうか?----と、そんな思いがよぎる。
読み物にしよう。事態が今後どこに向かうかはまだわからないけれど、経過報告という意味も込めて、テルマでライブ中継してみよう。それは同時に、僕なりに状況整理をする作業にもなる。事実は小説よりも奇なり。結果的にこの件が途中で頓挫したとしても、それはそれで笑えるじゃないか。
ということで、「転轍機を探す旅の記録」がここから始まる。
12月31日(月)
大晦日には紅白歌合戦をきっちり観る、というのが毎年の年越しの恒例。今年の目玉は……「あみん再結成」かな。人知れず期待して注目していたのものの、薄羽蜉蝣のごとく登場したかと思ったら、消え入りそうな声で唄い、あっという間に下がってしまった。終了。
紅白のトリを見届け、「ゆく年くる年」(この番組を観ていると南北に細長い日本列島を実感できる)を静かに眺めていたら、港に停泊している船が、年越しの汽笛を窓の外で鳴らした。
1月1日(火)
そして元旦。今年のわが身は果たしてどこに向かうことやら……もしP社の話が順当に進んでいたなら、今頃どんな気持ちで新年を迎えていただろう、などと詮無いことをつい考えてしまう。
結局のところ、今年もまた、僕の抱負は「行雲流水」になりそうだ。行く雲、流れる水の如しいくらあくせくしようとも、いや、その懸命なるあくせくも含めて、人は所詮「サムシング・グレイト(偉大なる何か)」が定める大きな流れの中の一滴に過ぎない。その都度必死になりながらも、しかし大局を見据えて我が身を俯瞰する目をもちたいといつも願う。
ここ数年、「行雲流水」という言葉は、僕の座右の銘である。
1月4日(金)
D社ミスターDより年賀状が届く。
「色々お待たせしてしまい、申し訳ありません。あとはタイミングだけの問題なのですが……」
ミスターは新年早々、CM撮影のために写真家・立木義浩氏とオーストラリアへ渡航中とのこと。
「帰国後、情勢報告も含めて一度お会いしましょう」
不思議なもので、時間が経てば経つほど、C社もD社もP社も自分の中で存在感を失くし、現実感がどんどん希薄になっている。まるで遠い昔の出来事のような感覚だ。一言でいうと「どうでもいい」。人もモノもそうだが、気持ちが離れる時というのはいつもこんな感じだ。先方が危惧していたのは、こういうことなのかもしれない。

1月10日(金)
A氏との約束の日。互いに多忙極まりないため、時間は連絡を取り合って決めようということになっていたが、この日僕は入稿作業があったため、P社銀座ビルに向かった頃は、すでに二二時を回っていた。
打ち合わせを終えて帰社したばかりのA氏と会う。
「今年もよろしくお願いします」と、年初の挨拶をすると、
「よろしくお願いできるかどうか、怪しいものだから困っちゃうよね」と苦笑交じりに言う。軽い冗談のつもりなのだろうけれど、新年早々のその言い草に、少々カチンとくる。
こちらの苛立ちを感じ取ったのかどうかは知らないが、A氏は僕を誘って夜の銀座へと繰り出した。クラブ、スナック、バーと、彼の行きつけと思しき店を次々にハシゴする。
A氏としては接待してくれているつもりなのかもしれないが、あいにく水商売の女には爪の先ほども興味のない身としては、年老いたバーテンのいる静かなバーで、バーボンでも傾けているほうがよっぽどよい。
媚びる女たちにいい加減嫌気がさしてそう言うと、A氏は銀座六丁目の裏通りにある「TARU」という古びたバーに向かった。薄暗い洞窟を思わせるその地下バーはいかにも僕好みで、カウンターのストゥールに腰を下ろすとようやく気分が落ち着き、僕はA氏の話を聞こうという気になった。
プレの顛末については年末の電話で聞いた通りで、しかも僕は別ルートで独自の情報も得ていたので、なおさら新しい発見などあるはずもなく、また、A氏の言葉に虚偽もなかった。
恐らく酔いと疲れもあって反応がひどく鈍くなっている僕に、A氏はこんなことをこぼした。
「うちは会社ができてもうじき三五年になるんだけど、今が大きな転換期なんだ。初期の頃はおれたちも若くてみんな尖っていたから、一流の仕事しかやらねえぞって感じで、だからこそクリエイティブ集団としての地位をここまで確立できたし、ガンガンやってこれたんだよね。でも、そういう経営方針なら、社員一〇人とか十五人とかその程度の規模でやるのが実は一番やりやすいんだ」
現在P社のスタッフは総勢五〇名を超える。日本のデザイン業界でこれだけの規模をもつデザインオフィスは、数社しかないだろう。いわゆる一流どころしか相手にしない「大手」だ。しかし、A氏は言う。
「社長もおれも、今が最も中途半端だと思っているんだ。縮小して昔みたいに小回りをよくするか、あるいは拡大して事業を増やしていくか、その選択を迫られている。もちろんおれたちは縮小なんか考えちゃいないし、今でさえ電通や博報堂から入る仕事だけで手が足りない状態なんだから、今後は最低でも一〇〇人規模まで会社の規模を拡大する予定なんだよね」
「五〇人増やすんですか? そりゃ大変だ」
「いや、実はそうでもないんだよ。コセムラクンに来てもらって雑誌編集の部門を立ち上げるでしょ、それからウェブのセクションも作る。そうすると自然にそれくらいの頭数は必要になるんだよね。……ただ」
A氏はそこで言いよどみ、焼酎を呷った。僕は特段先を促しもせず、カウンターに並ぶウィスキーのボトルをぼんやり眺めていた。
「決定的に足りないのは、プロデューサーなんだ」
「ふうん……いま何人くらいいるんですか」
「現在、肩書きとしては一〇人くらいだけど……本当の意味でプロデュース全般ができる人間というのは……いないな。もちろんおれたちは別だけど、要するにおれたちの下、次の世代の三〇代、四〇代のプロデューサーが育っていないんだよね」
むべなるかな。僕はそう思った。プロデューサーという職業は、企画立案から資金集め、交渉、折衝、営業、そして制作の細部に至るまで、およそ全てを見れる人間でなければ務まらない。ものすごく多面的で全体的、統括的で総合的な仕事だ(と思う。よく知らないけれど)。
P社はデザインプロダクションとしては一流である。が、そのスタッフの大半はデザイナーやコピーライターであり、彼らはいわば「職人」のようなもの。個々の技術やセンス、力量に関しては他社に抜きんでた超優秀なスタッフが揃っているのだろうが、それはあくまで職人であり、やれるとしてもせいぜい現場監督レベルだろう。その上に立つ統括的なプロデューサーという立場の人間がいない、というA氏の嘆きは、僕には容易に想像がついた。
ましてや、A氏達の世代のような叩き上げは別として、中堅にあたる四〇代前後のスタッフというのは、バブル華やかなりし頃に学校を出て社会人になった世代である。この層が「使えない」というのは、何もデザイン業界だけに限る話ではない(もちろんそうじゃない方もいらっしゃる)。
僕がぼんやりそんなことを考えていると、
「コセムラクンと会って話をしていてすごく感じたのは、この人ってものすごくプロデューサー向きだなーということなんだよね。物腰とか言葉遣いとかものの考え方なんか、もうすでに敏腕プロデューサーの域に達しているよ(笑)。知識の範囲は編集だけにとどまらないし、営業感覚やビジネスセンスも優れているし、何よりすごく礼儀正しいし(笑)」
「はぁ……」
確かにデザイン業界の人は、若いうちにさっさと独立してしまうケースが多いせいか、僕から見ると「社会人としてどうなの?」という感覚・礼儀の人が多い(もちろんそうじゃない方もたくさんいらっしゃるが)。
「D社の人とも話していたんだけど、正直なぼくらの気持ちとしては、将来的にコセムラクンにはメディアプロデューサーになってほしい、という思いがあるんです。だけど、コセムラクンはずっと編集をやりたい人だろうから、それを邪魔する権利はないしな、なんてことをこの間も喋っていたんだ」
「……僕はよく知りませんけど、編集者とプロデューサーというのは、ある部分とても似ているんじゃないんですか。編集者からプロデューサーになった人ってすごく多いですし。僕自身に関していえば、編集者という職業にとりわけ固執しているつもりはありません。編集という仕事は、どこにいようと何をしていようとできることだし、逆にいえばどんな仕事にも必ず『編集』という作業は関わってくるんです。デザインという要素があらゆる仕事と関わっているように。だからプロデューサーという職域は、今の僕の仕事と全く別のベクトル上にあるんじゃなくて……何ていうか、編集という職域をさらに発展させていった先にあるもののような気がするんですね。もしもそれが間違っていないなら、まぁ、プロデューサーという方向性は、僕としては全然アリだと思いますよ……」
酔いと睡魔で何だかもうよくわからない脳味噌になりながら、僕はそんなことを言った。A氏はやや安堵した様子で、
「改めて社長ともう一度相談するけど、うちとしてはコセムラクンを幹部候補として迎えたいと思っているから」
「……カンブコーホ?」
「つまり、取締役員の一人としてわが社に来てもらいたいと思っているんです」
「へえ」
「今回のことではタイミングがズレてしまって本当に申し訳ないけど、こちらとしてはそれくらい本気で考えていることなので、どうかもう少しだけ待ってもらえますか」
A氏はそう言うと、カウンターに額がつくくらい頭を下げた。
僕はというと、話が大きくなってんのか小さくなってんのかよくわからず、それより何より、今はとにかく眠くて帰りたい、ということしか頭になくて、とりあえずもぐもぐと聞き取りづらい生返事を返した。
憶えているのは、バーを出た時すでに午前四時を回っていたこと、それから、銀座で三軒もハシゴしておきながら、僕が払ったのは最後の店でぴらっと差し出した一〇〇〇円札一枚だけ、ということだった。
(2008年2月18日発行『TALEMARKETvol.55』より)
|